
核のゴミ調査隊(千葉県) 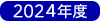

- 活動内容
- 勉強会、日本原燃(株)見学会
- 日時
- 2024年12月24日(火)~25日(水)
- 参加者
- 6名
- 団体の設立経緯・概要
- フィンランドのオルキルオトでは、『核のゴミ』を処分するための施設の整備が進んでいる。
一方、日本では『核のゴミ』の処分場を選定する第一段階の『文献調査』の報告や新たな自治体の参加表明があり、少しずつ報道されはじめた。
2011年の福島原発事故から13年が経過し、夏場や冬場の電力需給や風力発電やソーラー発電等による発電が注目を集めているが、原子力発電から生まれた「核のゴミ」は置き去りのままになっている。
代表は、先進的なフィンランドと日本の現状に疑問を感じ、高校生にアンケート調査を実施したところ、『核のゴミとは何か』、『核のゴミの何が問題なのか』など、基本的なことを理解していない方が多くいることを知った。そこで、文部科学省が行っている「トビタテ留学JAPAN」の留学探求制度を使い、フィンランドに短期留学し、オルキルオトのビジターセンターの見学や、フィンランドの人たちと交流する中で、『核のゴミ』に対する考え方、日本とフィンランドの核廃棄物の保存の仕方等を学んだ。
この留学をきっかけに、フィンランドで学んだ知見や経験をもとに、日本で活かしていくためには、核のゴミの『認知度』を上げ、多くの人たちと交流する機会を増やしていくことが重要だと考えた。
そこで、代表が通学している学校の先生や学生に、いま日本が置かれている状況を説明し、理解してくれた仲間と共に、『核のゴミ調査隊』を立ち上げた。
この団体の仲間とともに『核のゴミ』施設の状況、文献調査が行われた「地元の方々」の意識、同年代で活躍されている団体の方々と交流を通じて、学びを深め、SNSや学校・地域の行事などを通じて、核のゴミについて認知度を上げ、対話の機会を増やすことで、文献調査や核のゴミ処分施設の在り方など、エネルギーの入口から出口までを網羅的に考えていく機会を作りたいと考えていきたいと思う。
- フィンランドのオルキルオトでは、『核のゴミ』を処分するための施設の整備が進んでいる。
- 企画者の感想
-
今回初めて、日本の六ヶ所再処理工場を訪問し、フィンランドが行っている最終処分と、日本の再処理を中心とした核燃料サイクルの違いを比較することができました。六ヶ所村では、再処理や貯蔵、廃棄物の管理など、原子力に関する多岐にわたる取り組みが一つの地域で進められていることを実感しました。
施設を見学する中で、特に印象的だったのは、多くのスタッフや職員の方々が自分たちの仕事に誇りを持ち、安全管理や技術の向上に真剣に取り組んでいる姿でした。フィンランドの施設では、技術的な説明や管理体制に焦点が当たっていた一方で、六ヶ所では現場で働く人々の姿を間近で見ることができ、彼らの使命感を強く感じました。
原子力について高校生が直接学ぶ機会は限られていますが、今回の経験を通じて、フィンランドと日本の取り組みの違いや、それぞれの意義を深く理解することができました。今後は、この学びを活かし、原子力の現状や課題について周囲の人々にも伝えていきたいと考えています。 - 参加者の感想(アンケートから抜粋)
- 貴重な機会をありがとうございました!原子力発電について知れてよかったです。実際に自分の目で確かめてみたことで、原子力発電に対する理解や問題意識が高まりました。
- 必要と思っていてもなかなか実態を思い描けなかった高レベル放射性廃棄物処分に関する取り組みを見ることが出来て、大変興味深かったです。
- 今回初めて知ったことも多く、自分の中での「核のゴミ」に対するイメージ、偏見が変わり、これから意識していかなければならないと感じました。
- 今回の活動に参加して、全く知識のなかった核のゴミを深く知ることが出来ました。まだまだ分からないことは多いけど、これからもっと学んで深めていけたらいいと思いました。この活動に参加してよかったです。
- 施設見学前と比べて、廃棄物の処分に関して理解を深めることができました。かなり偏見をもたれやすい問題だなと感じました。
