
サイエンスカフェ 虹の会(青森県) 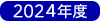

- 活動内容
- 勉強会、日本原燃(株)見学会
- 日時
- 2024年10月21日(木)~22日(火)
- 参加者
- 8名
- 団体の設立経緯・概要
- 原燃モニターを体験後、知人と共に学びのため設立。
年一度の学習会を開催している。
- 原燃モニターを体験後、知人と共に学びのため設立。
- 企画者の感想
-
初めての代表体験であり企画から実施に至るまで大変お世話になりました。また多方面にわたり、ご指導ありがとうございました。会員が学びを喜んでいたのが何よりの成果です。
しかしながら多くの反省点も残り、これまで学んできたことを復習したいと改めて思いました。このような機会をいただきありがとうございました。 - 参加者の感想(アンケートから抜粋)
- 幌延深地層研究センターで研究の任に当たられている方、また現場で働かれている方も含めて、初めて見学する方にも理解できるよう寄り添ってくれたことをありがたく思う。問題は増え続ける高レベル放射性廃棄物の処分地の選定だが、信頼関係をつないでスピードを上げて解決していくと確信している。
- 日本のエネルギー事情は化石燃料主体で、国際紛争が多発するため、安定供給が難しい。また、地球温暖化を防ぐため、再生エネルギー活用も進められている。原子力エネルギーはCO2をほとんど排出しないため、有効であるが、福島第一原子力発電所の事故の影響で多くの発電所が停止している。エネルギー資源の有効活用には原子力エネルギーの構成比を上げていく必要がある。
- 日本の原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の処分について研究が進んでいることがわかった。実際に人工バリアシステムや安全対策など体験して、もっと地層処分の候補地に手を挙げる自治体、理解してくれる国民(若年層を中心に)が協力的になる様期待している。電力を使う側もエコ、節電も考え電気を使用することが地球にやさしいのかなと思った。
- サイクル工場が稼働されておらず、最終処分する場所も決まらない状態に加え、高レベル放射性廃棄物の有害期間が極めて長いことから、原子力発電や原子燃料サイクルに理解できても、地元が最終処分場になることは不安が残るものと思う。多くの地点で文献調査が実施され、最後に最終処分地が決定され、サイクル工場の稼働開始を望む。幌延深地層研究センター職員のわかりやすい説明に感謝。
- 化石燃料に頼る発電はCO2排出の問題もあり、今後は再生エネルギーと原子力の二つが主流になっていく。特に原子力の回帰が急がれる。安心を前提とした原子力発電の推進を進めて行かなくてはならない。